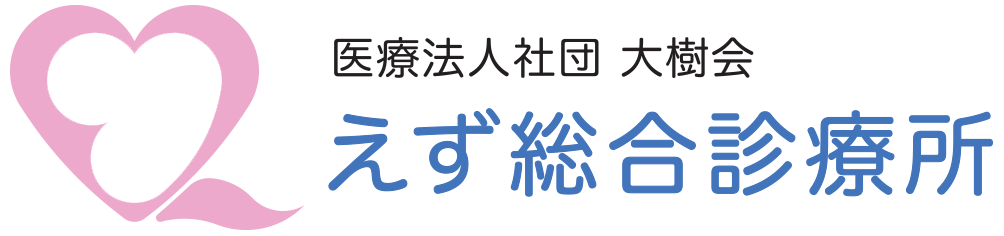運営規程
訪問看護ステーション えず 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、医療法人社団大樹会が設置する訪問看護ステーションえず(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1.ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管
理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在
宅療養ができるよう努めなければならない。
2.ステーションは事業の運営にあたって、必要な時には必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3.ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、
保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連
携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
4.ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整
備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
5.ステーションは、正当な理由なく訪問看護の提供を拒まないものとする。
6.ステーションは、訪問看護の提供の開始に際し、予め利用申込者又はその
家族に対し、運営規程の概要その他サービスの選択に必要な重要事項を記した
文書を用いて説明を行い、その同意を得るものとする。
(事業の運営)
第3条 1.ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示
書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2.ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、
看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、以下の通リとする。
(1) 名称:訪問看護ステーションえず
(2) 所在地:熊本市西区蓮台寺3丁目8番23号 カルムメゾン101号室
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者:看護師 1名(常勤)
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように
統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従
事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが
できるものとする。
(2)看護職員:看護師、准看護師 4名(2名常勤、2名非常勤)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当
する。
(3) 理学療法士:常勤専従1名
作業療法士、言語聴覚士必要に応じて配置する。
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 1.ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとす
る。
(1)営業日:通常月曜日から日曜日とする。但し12月29日から1月3日までを
除く。
(2)営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、訪問看護計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次の通りとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示
書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次の通りとする。
(1) 病状、障害・全身状態の観察
(2) 清拭・洗髪・入浴介助等による清潔の保持、食事介助及び排泄介助等日常生活の援助
(3) 医療的処置の実施及び指導(吸引、酸素吸入、カテーテル管理、褥瘡処置
内服管理等)
(4) 訪問リハビリテーションの実施と相談、指導
(5) ターミナルケア、認知症患者の看護
(6) 栄養、食事療法に関する相談、指導等
(7) 介護用品の紹介や工夫の仕方の実施
(8) 生活環境の調整と指導
(9) かかりつけ医師への連絡調整及び報告
(10) 在宅療養を継続するための必要な援助相談
(11) その他、医師の指示による処置と介護に関する相談
(緊急時における対応方法)
第10条 1.看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生
じた時は、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行うものとする。主治医へ
の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2.前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治
医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条 1.ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣
が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、その
サービスが法定代理受領サービスの場合、その1割、2割又は3割を徴収するものとする。
但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2.ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として支払いを利用者から受けるものとする
次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合の交通費、タクシー、公共交通機関等を利用した場合実費。ステーションの自動車を利用した場合は次の額を徴収する
実地地域を越えた地点から1Kmを超えるごとに50円を請求する。
サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させて頂きます。
24時間前までのご連絡の場合:キャンセル料は不要
12時間前までのご連絡の場合:当該訪問看護サービス提供の料金の25%を請求
12時間前までにご連絡のない場合:当該訪問看護サービス提供の料金の50%を請求
*利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません
3.訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、
利用料ならびにその他の利用料の内容及び金額に関して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。また利用料の支払いを受けたる時は、利用料とその他の利用料について記載した領収書を交付する。
(通常業務を実施する地域)
第12条 ステーションが通常業務を行う地域は、熊本市、嘉島町、宇土市、松橋町 他
(相談・苦情対応)
第13条 1.ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2.ステーションは、全項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
(事故処理)
第14条 1.ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2.ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3.ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 事業者において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束等の禁止)
第16条 1.事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2.事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3,事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する
(その他運営についての留意事項)
第16条 1.ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後3カ月以内の初任研修
(2) 年2回の業務研修
2.職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家
族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3.ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する次の記録
を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない(医療及び特
定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とす
る。
(1)主治の医師による指示の文書
(2)訪問看護計画書
(3)訪問看護報告書
(4)サービス内容
(5)市町村への通知
(6)苦情の内容
(7)事故の状況等
(8)身体拘束等に係る記録
(附則)
この規定は、令和6年8月1日から施行する。